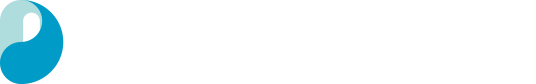Next Design V4.0 (4.0.11.50320) リリースノート
システム/ソフトウェアの開発を革新させる次世代設計ツール Next Design が、設計の生産性をさらに向上させる新機能を搭載しメジャーバージョンアップしました。 設計現場のニーズに応える操作性や表現力の向上、プロファイルの組み合わせやカスタマイズ対応によるプロセス資産の再利用性向上など、生産性を飛躍的にアップさせる数々の新機能でシステム/ソフトウェア開発を加速させます。
目次
新機能と改善の内容
現場ニーズに応える操作性と表現力
設計現場のニーズに応えて Next Design がさらに使いやすくなりました。 マルチタブでの複数モデル同時表示による作業効率向上、 ダイアグラムでの関連ハイライトや飛び越し表示による視認性向上、 ツリーグリッドでの色付けやメモ書きによるコミュニケーション円滑化など、 設計ツールとしての操作性や表現力を大幅に向上しました。
マルチタブ・フローティング表示
- 複数モデルのタブ表示により、別工程のモデルもすばやく切り替えて表示できます。
- ナビゲータやエディタからモデルをタブ領域にD&Dすると新しいタブで表示します。
- フローティング表示を使えばマルチディスプレイ環境を有効活用できます。
- モデルだけでなくトレースページやメタモデルのクラス図も同時に確認できます。

ダイアグラムの視認性・操作性向上
- 選択した関連線のハイライト表示や交点の飛び越し表示により、関連線の経路が複雑でも接続先が一目でわかります。
- ERダイアグラムでの整列ガイドが等間隔配置にも対応し、キー操作で位置調整もできるようになり、思い通りにシェイプを配置できます。
- シェイプへの画像貼り付け時に画像の縦横比に合わせてシェイプがリサイズされるようになり、画像の見た目が維持されます。
- マウスのホイール操作でダイアグラムをズームイン/アウトするとき、マウスが表示領域内にあるときはそのマウス位置を動かさずに拡大縮小できます。(シーケンス図、フィーチャツリー、クラス図も対応)

さらに使いやすくなったモデル編集操作
- モデルをエディタ上部にドラッグ&ドロップすることで、直感的にモデルを開けます。
- リッチテキスト型フィールド内のテキスト置換にも対応し、他のテキストと一緒に置換できます。
- 最近使ったプロジェクトをピン止めできるようになり、多数のプロジェクトを使っている場合でも、よく使うプロジェクトを素早く開けます。

色付けやメモ書きなどの表現手段拡大
- ダイアグラム以外でもモデルに色を設定でき、モデルを強調したり色分けしたりできます。
- ツリーグリッドでセルへのメモ書きや行番号表示ができ、レビューでのコミュニケーションも円滑にできます。
- メモはフィーチャツリーとコンフィグレーションエディタのセルでも使えます。

プロファイルの組織運用を加速
プロファイルは現場の知見が集約されたプロセス資産です。 要求定義、設計、テストなどの工程や製品系列ごとに定義したプロファイルを部品化してそれらを組み合わせるだけで、プロジェクト開始時に必要なプロファイル定義が手早く簡単にできるようになりました。 現場に合った設計項目名などのカスタマイズや組織によるプロファイル改訂への追従にも対応しており、組織的なプロファイル運用サイクルを加速します。

部品を組み合わせてプロファイル定義
- 作業工程や製品系列ごとにプロファイルを部品化して組み合わせることで、プロジェクトで必要なプロファイルを手早く簡単に定義できます。
- プロファイルの複数バージョンを管理して、プロジェクトごとに利用するプロファイルのバージョンを指定できます。
- プロファイルを共有フォルダでも公開でき、組織でのプロファイル配布も簡単です。
現場に合わせてプロファイルをカスタマイズ
- 部品化されたプロファイルを複数プロジェクトで再利用しつつ現場に合わせてカスタマイズすることで、プロジェクトごとの違いを吸収できます。
- プロファイルのカスタマイズにより、設計項目名の合わせこみや設計すべき情報の取捨選択ができます。
- プロファイルのマージにも対応し、プロファイルの改変を柔軟に行えます。
カスタマイズを維持してプロファイル改訂に追従
- 利用しているプロファイルが組織によって新しいバージョンに改訂されたときも、現場のプロファイルを簡単にアップデートできます。
- 現場に合わせてカスタマイズしている内容は維持したまま、組織によるプロファイル改訂を反映して追従できます。
- プロファイル改訂をプロジェクトに反映する前にプロファイルの変更差分を確認して反映タイミングを判断できます。
大規模・並行開発への対応強化
システム/ソフトウェア開発は日増しに大規模化が進んでいます。 Next Design を導入いただいている大規模・並行開発の現場でのニーズをフィードバックし、機能性はもちろん性能も大幅にアップさせて、ストレスのない操作性を実現しました。
モデルファイルの階層化
- 数多くのモデルファイルをサブフォルダで階層化することで、工程や機能などの単位でモデルファイルを整理できます。
- モデルファイルの階層化と合わせて、プロジェクトナビゲータのコンテキストメニュー[モデルファイルをインポート]と[モデルファイルを参照登録]を[モデルファイルを登録]に統合しました。
- 選択したファイルがModelsフォルダ以下にある場合は、ファイルの場所は変えずにインポートします。
- ただし、選択したファイルがModelフォルダ以下にあり、かつ、すでに参照登録されている場合は、参照登録のままとなりインポートしません。
- 選択したファイルがModelsフォルダ外にある場合は、インポートするか参照登録するかを選択できます。
- 選択したファイルがModelsフォルダ以下にある場合は、ファイルの場所は変えずにインポートします。

トレースページの性能改善
- トレースページの性能を大幅に改善し、大規模プロジェクトでもストレスなく操作できます。

別プロジェクトのインポート
- 別プロジェクトからすべてのモデルを一括でインポートできるため、変更開発時のモデル移行も簡単にできます。

Git連携の機能強化
- NDMerge によるコレクション順序のマージ処理ロジックを改善し、より自然な順序でマージできます。
- チェリーピック操作に対応し、コミット履歴から指定したコミットを現在のプロジェクトに適用できます。
- 「コミット時にマージによる不整合を検証する」などの便利なオプション設定が追加され、よく行う操作を簡略化できます。

その他数多くの機能アップ
Excelファイルへのエクスポート
- ツリーグリッドビューやプロダクトラインのコンフィグレーションをExcelファイルにエクスポートしてデータ活用できます。

EAインポート時のモデル更新
- 更新されたEAファイルを再インポートすることで、インポート済みのモデルに更新を反映できます。

オンプレミスフローティングライセンスのセキュリティ強化
- サーバー接続情報が埋め込まれたファイルをユーザーに配布してライセンス登録することで、サーバー接続情報を隠蔽できます。
- 特定PCのみ利用を許可することができ、許可されていないPCでのライセンス利用を制限できます。
- セカンダリサーバーを設定できるようになり、どちらかのサーバーで障害が発生してもアプリケーションの利用を継続できます。

ERダイアグラムの機能改善
- ダイアグラムで選択しているシェイプのパディング(選択しているシェイプと子シェイプの境界間の距離)を変更できるようになりました
モデルエディタの機能改善
- フォームやツリーグリッドのコンテキストメニューで、プロファイル関連のメニュー項目を1つのグループにまとめて「プロファイル」の下位に移動しました。
- フォームやツリーグリッドのコンテキストメニューで、アクセスキーがなかったアイテムにアクセスキーをつけました。
- モデルナビゲータ上に表示されていないモデルでもエディタ上から複製できるようになりました。
- エディタ上で選択している要素をもう一方のエディタ上で素早く選択できるようになりました。
- [メイン/サブエディタで表示]を実行したとき、その要素を対象エディタに表示している場合は、エディタの表示対象を切り替えずにその要素を選択するようになりました。
- 差分比較中にサブエディタ表示やインスペクタ表示を行った場合の振る舞いを次のように改善しました。
- 差分比較中にサブエディタを表示した場合、比較対象(変更前)と比較表示(色分け)がオフになり、現在のモデルとサブエディタが表示されるようになりました。
- 差分比較中にインスペクタを表示した場合、比較対象(変更前)と比較表示(色分け)の表示状態を維持して、インスペクタが同時に表示されるようになりました。
リッチテキストの機能改善
- リッチテキスト編集用コンポーネントの刷新して品質を改善しました。それに伴い次の点が変更されました。
- モデルエディタ上での行間が従来比1.25倍の高さで表示されるようになりました。
- リッチテキストに挿入できる画像形式が次のように変更されました。
- 変更前:bmp,jpg,jpeg,png,tif,tiff,gif,ico,wdp,hdp,wmf,emf
- 変更後:bmp,dib,jpg,jpeg,png,gif,tif,tiff,emf,wmf
- タブキーを押下した時の振る舞いが次のように変更されました。
- 変更前:キャレット位置が行の先頭の場合はインデントを挿入、それ以外はタブを挿入。
- 変更後:キャレット位置が行の先頭かつ後ろに文字列がある場合はインデントを挿入、それ以外はタブを挿入。
- 表の移動方法が変更されました。
- 変更前:表の左上に表示される移動アイコンをドラッグ・ドロップして移動します。
- 変更後:表全体を選択した状態で選択領域をドラッグ・ドロップして移動します。
- リッチテキスト編集中に複数箇所を同時に選択できないようになりました。
- HTML形式でのドキュメント出力時に、モデルエディタ上での見た目に近い行間高さで出力されるようになりました。(Word形式/PDF形式では従来通りの行間高さで出力されます)
- リッチテキストの表内でセルを分割する際、ダイアログで列数と行数を指定してできるようになりました。
- リッチテキストの編集に使用できるショートカットキーが追加されました。
- リッチテキストをテキスト検索する際、リッチテキスト型フィールドのHTMLフォーマットの値の中からテキスト検索する方式に変更されました。APIでリッチテキスト型フィールドに値を設定する際、HTMLフォーマットの値を設定するだけでTEXTフォーマットの値も自動設定されるように変更されました。これらにより、エクステンション開発者はリッチテキスト型フィールドのTEXTフォーマットの値を意識して整合させる必要がなくなりました。
プロファイル定義の機能改善
- プロファイルに対する表示名の追加に合わせて、プロファイルナビゲータのルート要素にはプロファイルの表示名を表示するように変更しました。(プロファイルのルートパッケージはインスペクタで確認できます)
- クラスの継承関係を削除する際、フィールドが多重継承となる場合は、エラーが通知され、継承関係を削除できないようになりました。
- フィールドを親クラスへ移動する際、フィールドが多重継承となる場合は、エラーが通知され、移動できないようになりました。
- クラス図・プロファイルナビゲータ上で、クラスを選択して一括削除を実行したときに、派生先クラスは削除せず、削除対象のクラスが直接持つ継承関係をすべて削除するようになりました。
- クラス図・プロファイルナビゲータ上で、パッケージを選択して一括削除を実行したときに、パッケージ内のクラスの派生先クラスがパッケージ外にある場合は、派生先クラスを削除せず、パッケージとの接点になる継承関係を削除するようになりました。
- 型の一括削除とパッケージの一括削除で派生先クラスを削除しなくなったため、一括削除時に同じフィールド名のフィールドを多重継承する場合があり、このときはユーザーに多重継承がある旨を通知して一括削除の処理をキャンセルするようになりました。
- ドキュメントフォームで、リスト要素を削除しようとしたときに、「リストの要素は削除できません。親のリストを削除してください。」というメッセージが出て削除できなくなりました。
- プロファイル保護状態でも、プロジェクトナビゲータのコンテキストメニュー[エクスポート]を利用できるようになりました。
- シーケンス図のライフラインに新しいマッピング定義を追加時に、ダイアログに表示される [マッピング対象] の初期値を [クラス] に変更しました。
ライセンス登録の機能改善
- Next Design 上のオフラインのライセンス登録・解除ダイアログからオフライン認証ツール「Offline License Activator」を直接起動できるようになりました。
最新の.NET8への対応
- アプリケーションのフレームワークを.NET8に更新し、最新の実行環境に追従しました。
APIの機能追加・改良
-
APIの追加・変更を行い、エクステンションによる拡張性を向上させました。詳細は下記ページをご確認ください。
修正した問題と制約事項
本バージョンで問題や制約事項の修正を行い、より安定した品質でアプリケーションをご利用いただけるようになりました。 修正した問題と制約事項の詳細は下記ページからご確認ください。
V4.0 アップデートに伴う注意点
V3.1 から V4.0 へのアップデートに伴う注意点をご説明いたします。 V4.0 へのアップデートを行わず V3.1 向けエクステンション開発を継続される場合も対応が必要な場合がございます。 以下の内容をご確認ください。
a) V4.0 へアップデートする方
拡張コンテンツのアップデートやオンプレミス版フローティングライセンスの利用方法の変更、一部APIの振る舞い変更があります。 詳細は次のページをご確認ください。
b) V3.1 を継続利用する方
V4.0 へアップデートせず V3.1 を継続利用するために V3.1 向けエクステンション開発を継続する場合、エクステンション開発プロジェクトの設定変更が必要となる場合があります。 詳細は次のページをご確認ください。
なお、アップデートはお客様の任意のタイミングで実施可能です。
アップデート方法
次のリンクからインストーラをダウンロードしてインストールしてください。アクセスの際はユーザー登録者の方にご連絡している "A" から始まるデンソークリエイトアカウントとそのパスワードを入力ください。
(今回のアップデートでは必須コンポーネントが変更されているため、Next Design のメニューからアップデートを行うことはできません)
以上です。